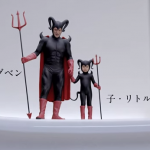test
118.90
”多聞言葉”シリーズ(探喫8‐44)
夫婦愛
前回の“多聞言葉”シリーズで「こだわり婚」について取り上げたが、新郎新婦に対する祝いの言葉でふれた“夫婦愛”について、考えてみたい。
結婚して、新しい家庭を築き、人生を歩んでいくことになった二人に、先輩として餞(はなむけ)の言葉としてアドバイスをしたときの内容である。
人は、まずは「好きだ!」という感情を抱き、一緒になりたいと思い結婚を決意する。しかし、「好き」という感情は移ろいやすいもの・・・。最初のうちは「あばたもえくぼ」というが、そのうち、「あばたはあばた」にしか見えなくなる。下手すると、お互いの粗ばかりが気になってしょうがないときだってある。
そのとき、大切なことは相手の中に「尊敬」できるものを見つけるという行為である。尊敬の念というものは、自分に足りない価値を相手の中に見出すことであるから、お互いに補い合うという気持ちが生まれるものだ。
ずいぶん前の『へルパ−人間学講座』だったと思うが、「好き嫌いの感情だったら、近所の犬や猫にでもある。隣のポチが、誰それを尊敬しているなどという話は聞いたことがない」と。つまり、尊敬という念は動物レベルにはない、人間だけの特徴である。
つまり、「好き」という感情的なレベルの“夫婦愛”を「尊敬」という精神的なレベルにまで高める必要があるし、それができるからこそ人間なのである。尊敬とは、その人の生き様に対する共感ではないだろうか・・・?お互いの人生の目的を語り合う時間をもつと、尊敬レベルの“夫婦愛”が生まれるのではないだろうか。
そしてもっと大切なことは、「信頼」である。では、信頼とは何だろう?自分と相手を分けない、一つだと思えることだと思う。では、信頼の絆とはどのようにして生まれ、強まっていくのだろうか・・・。
夫婦になると、夫婦であるがゆえに避けられない(運命共同体)、共有すべき人生体験に遭遇する。それは身近でいうと子供のことであったりとか、両方の親・兄弟のことであったりとか、その他様々なしがらみ・・・。
その共有すべき夫婦としての体験を二人で受け止め、協力し合い、労わりながら乗り越えていくプロセスで、夫婦のとしての共通の価値観が培われていくものだ。そのときに、「夫婦は対である」という言葉が実感できる。それが、信頼の絆であり、究極の“夫婦愛”だといえるのではないか。
仕事にも同じことがいえる。相手ができないことを代わりにやってあげると「好感」をもたれる。自分でやれるように指導をしてあげると「尊敬」されるようになる。相談を受けたときに親身に受け止めると「信頼」が生まれる・・・。
(H28.12.12)
119.10
”多聞言葉”シリーズ(探喫8‐44)
こだわり婚
最近の結婚式は、企画・演出力が凄い。
あたかも、芸能界のそれを観ているような感じだ。一生に一度の晴れ舞台、勧められれば、その気になってもおかしくない。(間違いなく、そうするだろう!)
職場結婚の若いカップルに招かれ、列席。挙式(約1時間)からはじまり、披露宴(2時間半)、そして二次会までセッティングされている。
最近の結婚式の特徴の一つでもあるが、仲人を立てず、いきなり新郎のウエルカム・スピーチから始まり、主賓の挨拶、乾杯の音頭と続く。二人の馴れ初めや自己紹介や小さい頃からのエピソードなどは、会場の大きなスクリーンに流れている。会場まえ庭園には、二人の小さい頃からの写真がたくさん飾ってあった。また、会場で流す動画やアルバムなどの編集など、二人のそれまでの人生がきれいに整理整頓されていて、記念になると思う。どれぐらいの時間とコストをかけて、企画・演出をしたのだろうと、職業柄、気になるところだ・・・。
ウエディングマーケットもご多聞に洩れず、成熟化し、独自性や多角化などの戦略をきちんと展開しないと厳しい状況にあるという。少子化等(非婚、未婚も含む)が進み、10年後には婚姻届出数は半分になると予測されているそうだ・・・。
「売上=来館数×成約率×単価」であるから、「来館数」が減少する以上、「成約率」と「単価」を上げるしかない。そこで活躍をするのが、専属プランナーである。カップルの要望を聞きながら独自の挙式を企画立案する仕事だ。つまり、“こだわり婚”に対する提案である。
以前に、某ハウスメーカーで自宅を建てたときのことを思い出した。営業マンに予算をいって、「その範囲内であれば建てたい」と話したら、予算通りの見積もりが出てきて、OK。問題は、その後である・・・。家の骨格ができて、外壁や内装に取り掛かるときに女性のコーディネーターを紹介される。そして、外壁で使う材料や内装の壁紙、キッチン・システム、照明器具やカーテンなどに対して、アドバイスを受ける。結果、アドバイスを受ける度に数十万ほど単価があがり、予算が500万円ほど増えたのを思い出した(結果、満足しているのであるが・・・)。営業マンのコーディネーターに対する気遣いが尋常でなかったので、その理由を聞くと、「私たちの仕事は成約率を高めることだから、どうしても単価を下げてしまい、利益貢献できないのです・・・」と。
身内びいきでいうわけではないが、凄くいい結婚式だった。最初に届いた案内状からすべてに“こだわり婚”の成果が出ていたと思う。(永遠の幸せを!)
(H28.12.6)
12月のお知らせ−大阪BV普及会、石井です。
バルーン(風船・ふうせん)を応援・参加してくださる皆さんへ
今年もあと1か月となり、体験会や大会にご協力をいただき、
ありがとうございました。
添付しました「 お知らせ 」にある日の練習会や体験会にも
参加していただき、新春1月22日豊中市のほくせつ大会や
来年も6月大阪大会と11月予定関西大会予定のご協力を、
引き続きましてよろしくお願いいたします。
大阪ふうせんバレーボール普及会 石井勝治
バルーン(風船・ふうせん)バレーボール、12月のお知らせ
2016・12・1
みなさん、お元気ですか!
急に冬がやってきました、ウイルスなんかに負けないでください!!
予防には、食事の栄養と口内清潔を心がけて体を温めて、スポーツなど楽しんで、
笑って自然治癒力をアップするのも良いようです!!!
豊中市で開催の「ほくせつ大会」は新春1月22日になりました、参加チームや
スタッフのみなさんも、体調に気を付けて笑顔で楽しみましょう!!
来年の大阪大会(6月)と関西大会(11月)に、早くも参加の申し込みチーム
あります、パラレルルールをよく理解しチームハンデ数18を確認してください。
《
大会参加のみなさんから、ハンデ数18をこえてるチームにきちんと指導する
ように、審判部へのクレームがきています。》
◎ 先月は、香川県“うたづ・バリアフリースポーツ体験会”と高松市“
スポーツ
クラブ教室”、かがわ総合リハビリ事業団のみなさんに「パラレルルール」普及。
長居障がい者スポーツセンター・練習日 (参加申込みは、お早めに!)
☆ ルールをもっと知りたい、審判員にチャレンジしてくださる、みなさんのため
夜間の時間を用意しました。チームでも、一人でも、参加できます。
⇒ 12月17日(土) 18:00〜20:30(2面)
12月25日(日) 15:30〜17:30(2面)
新春
1月
9日(祝、月)
11:30〜13:30(2面)
1月29日(日)
11:30〜13:30(2面)
*
淀川区、東淀川区、大正区、茨木市、島本町、豊中市、京都市の練習に参加したい、
見学に行きたい人は、普及会に連絡してください。
○ 普及会は、8日(木)東淀川区・むくの木学園“第2回目の体験会”
11日北九州市“やまびこの会”12日宮崎県“わたぼうし会”と 交流します。
☆ 「
ふれ愛 ♡ ささえ愛 ♡ 笑い愛 ♡ 」を大切にしています。
「風船バレー用品 ◎ お問合わせは、下記にお願いします。
風船(直径40?桃色)1個150− 大阪ふうせんバレーボール普及会 会長 石井勝治
鈴(特製)1個50− 〒533-0033大阪市東淀川区東中島1-17-5-637
空気入(ハンドポンプ)1本600− Tel/Fax 06−6815−3523
*新型・風船ゲージ(四つ折り)1個1,800− (MP-mail)ishiii.
1413 @ docomo. ne. jp
ゼッケン(肩ひも型.NO1〜6.8色)1枚1,050−」 (PC-mail)ishkatsu @ yahoo. co. jp
(日本バルーンバレーボール協会・設立準備室を、普及会事務局内に立ち上げてます。)
190.00
”多聞言葉”シリーズ(探喫‐41)
見切り
創業して数年も経たないうちに廃業に追い込まれる企業が意外に多いのに驚く・・・。
「“見切り”千両!」という言葉がある。相場世界での格言・・・。含み損状態にある株式などは、反転を期待して持ち続けるのではなく、手放して損切りをすべきだという教訓である。
対戦でいうところの撤退の見極め、決断であろう。起業には将来を描く楽しさ、夢がある。だが、廃業の“見切り”となると、そう簡単ではない。元々、自分の意思で始めたことだし、それなりの勝算があったはず。失敗とは思いたくないし、利害関係者との調整や社員の生活、残される債務など・・・。苦しい中での後始末は、経験した本人でないと分からないものだと思う。
すでに会長職にある経営者の方とお話をする機会があるが、「現役の当時を振り返ると、いろんな事業を手掛けたが、失敗ばかりだった。10に一つ成功できたかどうか・・・、だが、自慢じゃないが逃げ足だけは早かった」と。
つまり、“見切り”の決断である。起業は思い付きでもできるが、廃業や撤退はそう簡単なものではない。しかし、失敗から学ぶことは貴重だという。チャレンジに失敗は付きもの、「廉恥を重んじ、元気を振るう!」(三綱領)という精神で、体験を次に活かすことである。
“見切り”の哲学があるとすれば・・・。新規事業を始めるとき、成功のイメージを描くことは当然であるが、最悪の事態(撤退)を合わせて想定しておく必要があるという。そうなったときの“見切り”の条件を、前もって決めておくこと肝要だ。
1 背負えるリスクを事前に計算しておくこと(例えば、損失は1億が限度)
2 前もって期限を決めておくこと(3年で見通しが立たなければ撤退)
3 できる限り他人に迷惑をかけないこと(迷惑の許容範囲を見極める)
4 未練を残さないこと(日頃から全力を尽くしておく)
5 見栄やプライドに縛られないこと(自分の気持ちに正直であること)
6 ソフトランディングできる状態をつくること(軟着陸)
7 ケセラセラ(いい意味での開き直り)
“見切り”の先輩から教えて頂いた知恵である。もちろん、起業した以上はやり抜く覚悟は当然!その上での臨機応変さ・・・。無常の世の中である・・・。
(H28.11.28)